急げっ!
はそう思いながら港街の潮風の中をかけぬけていた。彼が目指す所は、街の小さな博物館だった。
そもそもの始まりは数日前までにさかのぼる。その時、静かなこの港街に妙なニュースと噂の波紋が広がった。
街の博物館に泥棒が入ったというのだ。
盗まれたものは、歴史的文化財の一部だとか、マニアの間では非常に高値で取引される大昔の動物の骨だとかいろいろ言われていたが、実際はそんなたいしたものではなかった。は自分自身の目と耳で確かめ聞いたのだから間違いない。盗られた物は、青い禁貨だった。
禁貨とは、バンカーと呼ばれる者が集める一種の硬貨だ。実際に物を売り買いすることは出来ないが、たくさん集めれば一つだけ願いが叶うらしい。通常は金色をしている。博物館にあったのは非常に稀少といわれる青色をしていた。一つ問題があるとすれば、博物館の青い禁貨は本物ではなくただのレプリカだったということだ。だいたい大きさだって普通の禁貨の二倍ほどはある。材質も違うし、偽物だということは一目瞭然だ。一体どこの誰がそんなものを盗んだのか、の心は好奇心でいっぱいだった。
しかし本当のところ、盗まれたものが偽物の禁貨であろうが、歴史的文化財であろうがには全く関係がなかった。犯罪が起きた! それだけではわくわくするのだ。あまり感心なこととは言えないのだろうが、は探偵のまねごとや推理小説が大好きだった。静かで平和なこの街に住んでいると小説に出てくるような事件など全く起きない。今回の泥棒事件はにとって絶好のチャンス、必ずや犯人を捕まえてやろうと彼は心に決めていた。
ところが今日、その青い禁貨泥棒が捕まったというのだ。先を越された。そのニュースを聞いたとたんはそう思ったが、禁貨を盗んだ犯人の顔も見てみたかった。そこで彼は大好きな推理小説を読むのも中断し、急いで博物館への道を走っているというわけだった。
スピードを保ったまま、はパン屋の角を曲がった。もし曲がった所に人がいると知っていたなら、彼はきっとスピードを落としていただろうに。
「うわっ!?」
ドンッ!
目の前に人がいるのを確認してからかけるブレーキは少し遅すぎた。あっ! と思った瞬間、は勢いよくその人と衝突していた。
「いったたた……。」
「ててて……。あっ、大丈夫?! ご、ごめんなさい!!」
慌てて謝る。相手は自分より少し年上の青年だった。青年は転んだ時に痛めたのだろう、尻をさすっている。が、を見るとにこっと微笑んだ。
「いやあ、オラは大丈夫だべさ。兄ちゃんのほうこそ大丈夫か?」
「あ、ああ……は平気やけど。」
怒られるかと思ったは少し拍子抜けして青年を見つめた。青年の赤い瞳には怒りの表情はうかがえない。むしろすがすがしささえ感じられた。
そんな好青年は立ち上がるとパンパンと服をはたき、を助け起こす。
「あ、ありがとう……。」
「兄ちゃん、そんなに急いでどこさ行くべ?」
「あっ、そうや! 、博物館行かなあかんねん。」
「博物館? それならさっき前を通って来たところだべさ。あそこで何かあるのか?」
「大アリや! この前、あそこに泥棒が入ってん。」
「泥棒!? そ、そりゃ大変だっぺ!!」
「いや、犯人はもう捕まったし、それにたいしたもんも盗られてないねんけどな。」
が事の次第を説明すると、青年はほお〜とうなずいた。
「それで、博物館に行くのか。」
「うん。犯人の顔、拝みに行ったんねん。」
「へえー、面白そうだっぺな!」
青年が少し目をきらきらさせてそう言った。
「……一緒に行く?」
「えっ? オラが行ってもいいのか?」
「あたりまえやん。らの街の博物館は老若男女入場無料や!」
が得意げにそう言うと青年は納得したようだった。彼は持っていた荷物をかつぎ直すと、の方に向かってにっこり笑って言った。
「オラはT-ボーン! よろしくな、えっと……」
「あっ、は。こっちのほうこそよろしくな、T-ボーン!」
が握手を求めるとT-ボーンは快く応じた。こうして二人は一緒に博物館に行くことになった。
二人が衝突した場所から博物館まではそう離れていなかった。小さなこじんまりした博物館で、当時は真っ白だったのだろう、今ではすっかり色あせてしまった壁がより古風な雰囲気を漂わせていた。扉は閉まっていて、『関係者以外入館禁止』の札が掛けられていた。
「……入っちゃだめだっぺさ。」
「うーん……。」
は窓の方にまわり、中をのぞいた。数人の職員が見える。青い禁貨を盗んだ犯人もいるようだったが、職員たちに囲まれてよく見えなかった。
「ま、ちょっとぐらいやったら怒られへんやろ。」
「えっ、中に入るんだべか?」
「当たり前。ここまで来て引き下がれるか。」
はそう言うと扉のほうに戻り、ぐっと力をこめて押した。鍵はかかっておらず、扉は少しきしみながらゆっくり開いた。
「こんにちわー。」
と、職員たちの目が一斉に彼らに注がれた。は一瞬ひるんだが、禁貨泥棒の犯人を見つけるとその好奇心を抑えることはすでに不可能に近かった。
「うっわー、あんたらが犯人かー!」
「な、なんだてめぇは!?」
泥棒は二人組みの男だった。一方は大柄で、鉄の帽子のようなものをかぶっている。もう一方は大柄な男とは反対にひょろりとやせていた。はそんな二人を見てさらに言う。
「あんなー、小説に出てくる怪盗はみんなバシッと犯罪を決めたあとにカッコええ探偵にトリックを暴かれて御用やねんで? お前らもうちょっと粘らんか……。」
のそんな言葉を聞いて泥棒たちは非常に何か言いたげだったが、博物館の職員にとがめられ、口をつぐんだ。
「君たち、扉の注意書きが読めなかったのか?」
妙に光を反射するめがねをかけた、厳格そうな若い職員が厳しい口調でそう尋ねる。はどこ吹く風だった。職員を無視して犯人たちに近づく。無視された職員は不服そうな顔で今度はT-ボーンの方を見たが、彼は白い歯を見せ、
「ま、細かいことはいいっぺよ!」
と言ったきりだった。
「へえーっ、ほんまにおっさんらが盗んだん? めっちゃ間抜けそうやけど……」
「誰が間抜けだこのガキ!」
「あっはっは、間抜けだから捕まっちまったんだべさ?」
「おお、なるほど。」
「だっ! だから誰が間抜けだ! くそガキー!」
大柄な男が縄から逃れようともがいたが、むなしい抵抗に終わった。どうやら手錠もかけられているようだ。
「で、おっさんら名前は? それから、犯行の動機は? あの青い禁貨に何かあるんか?」
「こ、こら少年! そういうことは大人の仕事だ。速やかに家に帰りなさい。」
が犯人たちに質問を始めると、別の職員がそう言って彼を制した。だがはうけつけない。
「まあええやん、ちょっとぐらい。なあ、名前、名前は?」
「何でオレたちが答えなきゃいけないんだ。」
やせているほうがボソッと言う。と、T-ボーンが助け舟を出した。
「名前も言えねっぺか。」
この言葉に男たちはカチンときたのだろう。大柄な男がわめいた。
「なんだと?! オレ様は天下の最強バンカー、アブラミー様だ!! 覚えてやがれっ!」
「そしてオレはアブラミー親分の一子分、スージー・ニック様だ! わかったかガキんちょ!」
その剣幕に一瞬場にいた全員がしんとなった。が、すぐにが口を開く。
「お、おっさんらバンカーなん!?」
アブラミーとスージー・ニックは自慢げにうなずいた。やや驚くを見て、T-ボーンも続ける。
「オラだってバンカーだべ。」
はさらに驚いた。今までバンカーについてあまり良い噂は聞いたことがない。盗み、喧嘩、残虐なものにいたっては人殺しなども。実際目の前にいるバンカーたちは盗みを働いた。が、自分のすぐ横にいるこの青年は? 好奇心旺盛で、満面の笑顔を人に見せることができる、このバンカーは? の心に矛盾した考えが広がる。考えれば考えるほどバンカーというものがわからなくなってくる。彼は一瞬その思考の渦に巻き込まれそうになった。そしてはっと気付く。
あかんあかん。今はそんなことを考える時やない。かの有名は名探偵たちはこんなところで動揺したりするもんか。
はそれを思い出して一つ咳をし、冷静さを保った。
「じゃあアブラミーとスージー・ニック。なんで禁貨を盗んだんや。」
彼らは答えない。スージーは不安げな表情でアブラミーの方を見た。彼の頼りになる親分は、激しく首を振っただけだった。
「それを今私たちが聞いていたんだよ。さあ、あとは我々が何とかするから、君たちはもう帰りたまえ。」
「ちょ、も、もうちょっと!」
は抵抗したが、メガネの職員は彼とT-ボーンを無理矢理扉のほうへ連れていった。後ろでは他の職員達が再びアブラミーたちに詰問を始めたようだ。
「で? どうして青い禁貨を盗んだ?」
「へっ! 知るかってんだ!」
「じゃあ、一体どこに隠した! 青い禁貨はどこにあるんだ!」
はその言葉にハッと振り向いた。そしてええーーっ! と叫ぶ。
「青い禁貨、戻ってきてないんか?!」
はメガネの職員の手を振り切り、再び犯人たちのほうにかけよった。T-ボーンもあとに続く。
「青い禁貨、戻ってきてないんか!」
彼はもう一度同じことを尋ねた。アブラミーはうす笑いをうかべ、
「あんな偽物、どうなったって知るか。」
と言い放った。
「……そりゃまあそうだべな。なあ、おっちゃんら、そんな偽物の禁貨なんか大切なんだっぺか?」
T-ボーンが職員達に向かって尋ねる。
「え? あ、ああ。あの青い禁貨は確かに偽物だがな、今は亡き私の友人が……彼は細工師だったんだが、その人が博物館の開館祝いにこれでよければ飾るようにと贈ってくれた物なんだよ。」
彼の問いに答えたのは、職員の中では一番老いている男だった。どうやら彼がこの博物館の館長らしい。目を細めて青い禁貨のいわれを語った。
「当時、まだ目新しいものがなかったこの博物館にとって、青い禁貨は一番の目玉だった。確かにそれは偽物には違いなかったが、そのできばえ、大きさを除けば本物と見間違うぐらいだった。非常に精巧に作られていてね……。確か、彼も以前はバンカーだったとか。結局願いは叶わずだったそうだがそのほうが良かったかもしれん。彼には細工師の方が向いていたからね。あの青い禁貨は、そんな彼の素晴らしい作品の一つなんだよ。失ってしまったのはじつに惜しい……。」
館長が話し終えてしばらくは誰も何も言わなかった。
「そんなに大事なもんやったんか……。」
が沈黙を破り、そして館長はうなずいた。
と、は見た。泥棒たちがなにやら不穏な動きをしているのを。スージー・ニックがアブラミーに何かをささやき、その直後アブラミーは彼の子分をしかりつけた。するとスージーはまたアブラミーに何かをささやき、そして彼自身のポケットを目で示した。
「なんや、何かあるんか?」
は迷わずスージーが示したポケットを調べた。
「わっ、わっ、何するんだ! ちょっと、やめろって小僧ーっ!!」
スージーの抵抗はむなしく、はすぐに何かを手にした。何か、紙切れのようだ。乱暴に四つ折りにされている。開いてみると、不規則並べられたいくつもの文字と奇妙な絵とが目にとびこんできた。
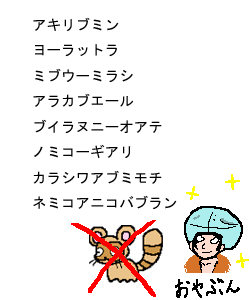
「なんだこりゃ?」
「スージーーっ!」
「す、すいません親分ーー!」
「何、何だべか?」
T-ボーンが紙切れをのぞきこむ。だが、その支離滅裂な文字の意味は彼も理解しかねるようだった。
「暗号……かなあ?」
「だども、何の暗号だべ?」
「うーん……。」
博物館から盗まれた青い禁貨。捕まった犯人の一人が持っていた謎の暗号。そして盗まれたまま戻らぬ禁貨の行方。とすれば、暗号に示されているものは……
「青い禁貨の隠し場所やな!」
その言葉で明らかにスージーが反応した。間違いない。この暗号を解けば、きっと青い禁貨のある場所がわかるに違いない。
「それにしても、こんな暗号、どうやって解いたらええんや?」
「けっ。小僧に分かってたまるか!」
スージーが言い捨てる。が何か言い返そうとした瞬間、誰かに肩をつかまれた。
「さあ君たち、もういい加減にしなさい。その紙を私たちに渡して早く家に帰るんだ。」
メガネの職員の言葉はとげを含んでいた。これ以上ここにいるのは困難かもしれない。だが、せっかく手に入れた手がかり――この暗号文をみすみす手放すのも惜しかった。
「ねえ、お願いします。せめてこの暗号文だけでもコピーさせてくれませんか。」
職員たちは顔を見合わせた。その表情からはあまり良い返事は期待できそうにない。だが、館長は言った。
「まあ良いではないか。誰か事務室に行ってコピーを取ってきてあげなさい。案外この子たちが暗号を解くかもしれんよ。」
思わずは喜びの声をあげた。そしてすぐに一人の職員に紙を渡すと、職員はしぶしぶ博物館の奥にある事務室へ入っていった。
「館長さんめっちゃええ人やなあ! ありがとう!」
館長はにっこり微笑んだ。
「しっかし本当に意味不明な文だべさーこりゃ。」
紙とにらめっこをしていたT-ボーンがうめいた。
暗号文のコピーを受け取った後、二人は博物館を後にし(というよりもなかば追い出されて)近所の公園に来ていた。ベンチに腰かけ暗号文の解読を始めた二人だったが、作業はなかなか進まない。
「今度はにかして。」
「オラ、頭使うのはどうもあんまり得意じゃないっぺ。」
T-ボーンは苦笑し、紙切れをに渡した。
「うーん……。」
何度見ても意味がわからない。難問にぶつかった時の癖で、はブツブツつぶやきだした。
「アキリブミン
ヨーラットラ
ミブウーミラシ
アラカブエール
ブイラヌニーオアテ
ノミコーギアリ
カラシワアブミモチ
ネミコアニコバブラン
……これらの文字と、そして紙の右隅に描かれた二つの奇妙な絵……。一方にはでっかい×印がかかってるな。」
「オラには何か変な動物と、男に見えるけどな。」
「うーん、下手くそな絵やなあ! だけど、こっちの絵、これはさっきの犯人の一人に見えんこともないな。」
確かに描かれている絵の×印のないほうは禁貨泥棒の一人のようだった。は隣のT-ボーンに尋ねる。
「名前なんだっけ?」
「アブラミー、とかじゃなかったか?」
「こっちの絵は何やろう?」
耳と目が二つずつ、それから口と鼻、四本の足。動物には間違いなかった。しかし、何の動物かは皆目見当がつかない。二人ともしばらく黙り込んでしまった。
「丸い耳と……ずんぐりした尻尾、目の周りの黒い模様……。」
あっ! と、T-ボーンが叫んだ。
「タコ!?」
「なんでやねん!!」
「えっ……だってこの辺とか、タコに見えねーか?」
「お前の中のタコってどんなんや……。」
は呆れたが、どうやら本気で間違えたらしいT-ボーンはぽりぽりと頭をかいた。
「うーん、タコじゃないとすると一体なんだべさー?」
「まあ×印がついてるあたり、この絵は関係ないんかもな。」
T-ボーンはその言葉にはかまわずにうなっていた。そしてまたあっ! と叫んだ。
「タヌキだっぺ!!」
「いや、だから関係ない絵かもしれんて……。」
はそう言ってその絵にふっと視線を落とした。なるほど、タヌキに見えないこともない。
「タヌキ……かなあ?」
「タヌキだべ。」
「じゃあ、タヌキ(仮)ってことで。」
「うん、タヌキ(仮)ってことにするべ。」
あとは暗号を解くだけだった。は再び事件の重要な鍵となるたった一枚の小さな紙切れに視線を落とした。
T-ボーンは横でうーむとうなっている。彼自身、謎解きは苦手だ、と言っていたからあまり期待はできないだろう。
(ここはが解くしかないか……。)
長い間沈黙が続いた。時々T-ボーンやがうーん、とうめく声が虚しく響く。
と突然が叫んだ。
「そ、そうか!」
「わかったんだべか?!」
はうなずいた。そして、彼はある方向を指した。
「あっちだ!」
To be continued...
どちらかに進んでください。
a.教会 b.博物館
